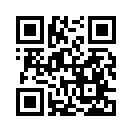2023年07月17日
7月14日(金)の日記 街歩き 岩手県一関市千厩町と一関市街
2023.07.14 岩手県一関市千厩と一関市街の保存建築物見学
◇明治時代から戦前にかけて建てられた貴重な近代建築を見学に岩手県一関市を訪ねた。今は一関市になっている旧千厩町と一関駅前地区の市街地を探訪した。
往きは新幹線と路線バスを利用、帰路は路線バスと在来線の各駅停車の旅を味わった。
【一関市千厩の町】
千厩町は一関と気仙沼を結ぶ街道の中間地にあり藩政時代は伊達藩の宿場町としてにぎわった。2005年までは岩手県東磐井郡にあった、郡内の中心的な町であったが現在は一関市と合併している。昭和時代中期頃までは養蚕業・たばこ産業が盛んで町における主要産業であった。現在の千厩高校の前身は養蚕学校であった。
現在「ドラゴンレール」の愛称がつけられているJR大船渡線は一関から東に向かったとたん大きく北に向かい猊鼻渓や摺沢を経由してクランク状に南に戻り千厩に繋がる。なんとも大きな迂回ルートだが、誰でも予想する通りかつて鉄道を敷設したころの摺沢と千厩出身の代議士の政治力によるもので、いわゆる「我田引鉄」の代表例とされている。というわけで一関駅から千厩駅にゆくには迂回する鉄道より直進するバスの方が早い。今回もバス利用であった。
千厩には、かつて国鉄大船渡線に「むろね」という名の急行列車がありこれに乗ってと、一関から気仙沼へ車で向かう時にいずれも通過したことがあるが降りて街の中を散策したのは今回が初めてである。
歴史上、千厩は奥州の覇者藤原秀衡の放牧地であり源義経がまたがった名馬の産地として有名だそうな。さらに、16世紀末、豊臣秀吉の増税に抵抗して起きた金山一揆がありこれも有名とのことだがよく知らなかった。
■旧専売局千厩煙草専売所(せんまや街角資料館)
明治30年全国に61ケ所に設置されたたばこ専売事務所だが、現存はここだけ。旧東磐井郡、気仙郡の葉煙草栽培の歴史を目にすることのできる唯一の産業遺構。
・玄関の<波形破風>が特徴。フィニアル、持送り、メガネ石






■旧横屋酒造・佐藤家住宅(千厩酒のくら交流施設)
25棟が国登録文化財。
・西洋館は大正13年建築。中央ペディメント風







■義経の愛馬「太夫黒」
義経の愛馬<太夫黒>発症の地として有名。せんまや馬事資料館やすぐ近くの交差点の角の小さなエリアにゆかりの銅像などがあった。


■千厩の町。シャッターを下ろした店が目立つ



■千厩から一関への復路もバス利用。途中で盲導犬をつれたお年寄りが乗って来た。犬もまわりも慣れた感じで普通に接していたのが素晴らしい。

【一関市中心街(駅前)】
現在の一関市は、2005年(平成17年)に7市町村の対等合併で出来た三代目の一関市である。県内では宮古市に次ぐ広大な市域を持つ自治体となり、宮城県と秋田県に接している。人口は約11万人で県内では盛岡市、奥州市に次ぐ規模である。
■街並み
駅前の中心街は街路が整備され、きれいに整頓された街という印象である。



■大槻三代ファミリー。蘭学者大槻玄沢、漢学者大槻盤渓、国語学者文彦の像が駅前に鎮座していた




■戦後の台風による大洪水 のモニュメント。
カサリン・アイオン台風により北上川が大洪水を起こした時の水位を示した説明板

■もちの里一関。昼食は<もち>。伊達藩にはもちの文化が受け継がれており現在もこのエリアでは多彩なもち料理が伝統食。ということで昼食は、お雑煮と単品。単品は(この店では)、あんこ・ごま・くるみ・ずんだ・じゅうね(えごま)・エビ(本日売り切れ)・ショウガがあった。




■日本基督教団一関教会
1905年(明治38年)創立のプロテスタント教会。現在の建物は1929年(昭和4年)の建築物。1947年・48年の大洪水にも耐えた。登録有形文化財。

■世嬉の一酒造



◇明治時代から戦前にかけて建てられた貴重な近代建築を見学に岩手県一関市を訪ねた。今は一関市になっている旧千厩町と一関駅前地区の市街地を探訪した。
往きは新幹線と路線バスを利用、帰路は路線バスと在来線の各駅停車の旅を味わった。
【一関市千厩の町】
千厩町は一関と気仙沼を結ぶ街道の中間地にあり藩政時代は伊達藩の宿場町としてにぎわった。2005年までは岩手県東磐井郡にあった、郡内の中心的な町であったが現在は一関市と合併している。昭和時代中期頃までは養蚕業・たばこ産業が盛んで町における主要産業であった。現在の千厩高校の前身は養蚕学校であった。
現在「ドラゴンレール」の愛称がつけられているJR大船渡線は一関から東に向かったとたん大きく北に向かい猊鼻渓や摺沢を経由してクランク状に南に戻り千厩に繋がる。なんとも大きな迂回ルートだが、誰でも予想する通りかつて鉄道を敷設したころの摺沢と千厩出身の代議士の政治力によるもので、いわゆる「我田引鉄」の代表例とされている。というわけで一関駅から千厩駅にゆくには迂回する鉄道より直進するバスの方が早い。今回もバス利用であった。
千厩には、かつて国鉄大船渡線に「むろね」という名の急行列車がありこれに乗ってと、一関から気仙沼へ車で向かう時にいずれも通過したことがあるが降りて街の中を散策したのは今回が初めてである。
歴史上、千厩は奥州の覇者藤原秀衡の放牧地であり源義経がまたがった名馬の産地として有名だそうな。さらに、16世紀末、豊臣秀吉の増税に抵抗して起きた金山一揆がありこれも有名とのことだがよく知らなかった。
■旧専売局千厩煙草専売所(せんまや街角資料館)
明治30年全国に61ケ所に設置されたたばこ専売事務所だが、現存はここだけ。旧東磐井郡、気仙郡の葉煙草栽培の歴史を目にすることのできる唯一の産業遺構。
・玄関の<波形破風>が特徴。フィニアル、持送り、メガネ石

■旧横屋酒造・佐藤家住宅(千厩酒のくら交流施設)
25棟が国登録文化財。
・西洋館は大正13年建築。中央ペディメント風
■義経の愛馬「太夫黒」
義経の愛馬<太夫黒>発症の地として有名。せんまや馬事資料館やすぐ近くの交差点の角の小さなエリアにゆかりの銅像などがあった。
■千厩の町。シャッターを下ろした店が目立つ
■千厩から一関への復路もバス利用。途中で盲導犬をつれたお年寄りが乗って来た。犬もまわりも慣れた感じで普通に接していたのが素晴らしい。
【一関市中心街(駅前)】
現在の一関市は、2005年(平成17年)に7市町村の対等合併で出来た三代目の一関市である。県内では宮古市に次ぐ広大な市域を持つ自治体となり、宮城県と秋田県に接している。人口は約11万人で県内では盛岡市、奥州市に次ぐ規模である。
■街並み
駅前の中心街は街路が整備され、きれいに整頓された街という印象である。
■大槻三代ファミリー。蘭学者大槻玄沢、漢学者大槻盤渓、国語学者文彦の像が駅前に鎮座していた
■戦後の台風による大洪水 のモニュメント。
カサリン・アイオン台風により北上川が大洪水を起こした時の水位を示した説明板

■もちの里一関。昼食は<もち>。伊達藩にはもちの文化が受け継がれており現在もこのエリアでは多彩なもち料理が伝統食。ということで昼食は、お雑煮と単品。単品は(この店では)、あんこ・ごま・くるみ・ずんだ・じゅうね(えごま)・エビ(本日売り切れ)・ショウガがあった。
■日本基督教団一関教会
1905年(明治38年)創立のプロテスタント教会。現在の建物は1929年(昭和4年)の建築物。1947年・48年の大洪水にも耐えた。登録有形文化財。
■世嬉の一酒造
Posted by OOAKAGERA at
20:25