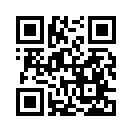2022年12月12日
12月12日(月)の日記 大河ドラマと後鳥羽上皇
2022.12.12 またまた長文の駄文です。時間があったらどうぞ
◇大河ドラマ「鎌倉殿の13人」はいよいよ大詰めを迎えあと1回で終了である。承久の乱寸前まできたがあと1回でどこまで進むのか楽しみである。主人公北条義時は承久の乱の後もしばらく生き続けたはずだがその物語はあと1回にはおさまらないだろうし・・・。
◇ところでドラマに出てくる後鳥羽上皇は鎌倉幕府との対立ばかりが描かれているが、実はとんでもないスーパーマン(スーパー神?)である。和歌に長じているのは知られたところだが、19歳という若さで息子の「土御門天皇」(つちみかどてんのう)に天皇の座を譲り、和歌以外にも書画、管弦(琵琶など)、蹴鞠、水練(すいれん)、相撲、笠懸(かさがけ:弓矢の騎射)など諸芸を磨くことに力を注いだ。さらに武道にも秀で、自ら日本刀を打ったと伝えられるほど、歴代皇族の中でも異彩を放つ、天才肌の天皇である。
◇中でも、銘刀「菊御作」(きくごさく)は、後鳥羽上皇が残した最も偉大な文化遺産のひとつである。菊御作は数振現存しており、国宝・重要文化財に指定されている。
後鳥羽上皇がらみの雑文復刻の復刻です。
【復刻】
2022.01.12
今年の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」は、北条義時を主人公に平安時代末期の武士の台頭から、鎌倉幕府の樹立、貴族側の反撃承久の乱あたりまで描かれるものと思う。後半は後鳥羽上皇も目立つ役回りになると予想する。2年前の正月に掲載した雑文を再度アップ。
<追記>物語は承久の乱まで行かずに、もっと前の時点までで終わるのかもしれない。
【復刻】
2020年1月の記事を復刻
◇気まぐれ録画のテレビ番組を見た。面白かった。NHK[BSプレミアム] 1月4日(土) 午後7:00~午後9:00 新春英雄たちの選択スペシャル「百人一首」
◇お正月の風物詩、カルタでおなじみの「百人一首」(ここでは小倉百人一首を指す)。1人1首100人の和歌が納められている。平安時代を中心に7~13世紀のスター歌人が勢ぞろいした、いわば王朝ベストアルバムである。
<番組紹介は以下の通り>
■百人一首!名歌集はなぜ生まれたのか? 選者・藤原定家と後鳥羽上皇の愛憎渦巻くドラマ。選歌に秘められた謎。競技かるたの極意とは?百人一首を徹底解剖!
■百人一首は平安時代を中心に500年にわたる王朝の名歌を収めたベストアルバム。だが、この歌集、よく知られているようで実は謎が多い。名歌はどうやって生まれたのか?天皇から僧侶までの歌人は、なぜこの100人が選ばれた?番組は、選者・藤原定家と後鳥羽上皇の愛憎渦巻くドラマを軸に、百人一首誕生の秘密に迫っていく。クイーンとのかるた大会も開催。王朝の雅に浸りたい歴史ファン必見!百人一首を徹底解剖する特別企画
■百人一首は王朝絵巻、古代~中世550年の歌には時系列的に読み手に番号がつけられている。1番は天智天皇、17番在原業平、57番紫式部、86番西行、最後99番後鳥羽院、100番その息子の順徳院といった具合である。王朝時代のルーツから終焉までを網羅している。
■百人一首は藤原定家が選んだ秀歌撰である。定家は19歳から74歳まで自筆の日記を書いている。明月記である。それによってかなりの「人となり」がわかる。生まれは平安時代の末期、武士の台頭・源平の合戦の時期を生きている。まわりと相いれない定家の斬新な和歌にその才能を見抜いたのが18歳年下の後鳥羽上皇である。上皇は乱世により大きく人生を振り回された。わずか4歳で皇位についたが、安徳天皇とともに海中に沈んだ三種の神器の剣がない状態での即位であった。19歳で退位し上皇となってからは蹴鞠や歌舞音曲、刀剣制作などに打ち込んだ。そしてそれ以上にのめりこんだのが和歌であった。歌の力で失われつつある王朝の権威を取り戻そうとした。そのために必要だったのが時代の先を行く定家の斬新な和歌だった。2人の化学反応が王朝文化に革命を起こす。しかし時代の流れに巻き込まれ2人は仲たがいする。
<以下はいつもの私の雑文>
◇テレビ番組では途中に再現ドラマが入り、これが結構面白かった。膨らませて連続ドラマが作れそうだが、時代的に視聴率がとれないので大河ドラマにはならないでしょうね。
◇小倉百人一首は勅撰の和歌集ではないが、承久の乱を起こし、晩年は隠岐の島に流刑となった後鳥羽院が大きくかかわっていたというドラマの筋書きはうなづける。対立したとはいえ和歌の同好の士、後鳥羽院には心の底では最後には許しあっていたのでしないか。百人一種には「風」がうたわれた和歌が多いがそれは「隠岐の風」を意識していたのではないかという。先年亡くなった我が家のばあちゃんは、テレビで相撲をみていて隠岐の海がでてくると、しょっちゅう後鳥羽院の歌を声高に歌っていた。「われこそは新島守よ隠岐の海の 荒き波風心して吹け」。元気いっぱいの後鳥羽院は、さぞかし都に戻りたかったでしょうね。テレビの再現ドラマでは「隠岐の院」と呼んでいた。すんなり受け入れられた。
◇百人一種のカルタは最近はほとんどやってないが、一時は正月に集中的にやった。いつまでも頭に入らない歌があり、上の句を詠んで下の句がわかるのはせいぜい70%くらいだった。今はもうさらに忘れているものが多い。家族それぞれひいきの札がありそれだけは他人にとらせまいとがんばった。
◇歌の解釈はわからなくても耳から入って覚えたものは結構覚えているとも言える。英語も文法など後回しでいきなり会話・ヒアリングから入った方が身につくのには早道かも。
◇小学生の頃は坊主めくりをした。今時こんな遊びをする家庭はほんとに少ないのでしょうね。
◇宝塚歌劇団の生徒さんには百人一首からつけた名前が多かった。昔はほんとに百人一首カルタが広く親しまれていたと想像できる。
◇昔の和歌には「歌枕」が多く読み込まれている。仙台の近くでは、末の松山、沖の石、松島の雄島など。名取にお墓がある実方中将(藤原実方朝臣・51番)は「歌枕見てまいれ」と言われて陸奥の国に来た。百人一首にも親しみがわく題材がある。
◇小倉百人一首には数々の謎が隠されているといわれている。推理小説の題材にもなっている。選ばれた歌人は不幸な人生を歩んだ人が多いとかあまりに下手な歌が選ばれているとか。人気があって、広くみんなの目が行き届くといろいろ詮索することになるのだろう。
◇「親子して千と百とを詠みえらみ」こんな句があったと思う。おかげで、親の藤原俊成→千載和歌集、子供の藤原定家→百人一首と簡単に覚えられた。 → 【訂正】 御父子して千と百とをおんえらみ が正しいようだ
◇正月、肩の凝らない番組を楽しんだ。
◇大河ドラマ「鎌倉殿の13人」はいよいよ大詰めを迎えあと1回で終了である。承久の乱寸前まできたがあと1回でどこまで進むのか楽しみである。主人公北条義時は承久の乱の後もしばらく生き続けたはずだがその物語はあと1回にはおさまらないだろうし・・・。
◇ところでドラマに出てくる後鳥羽上皇は鎌倉幕府との対立ばかりが描かれているが、実はとんでもないスーパーマン(スーパー神?)である。和歌に長じているのは知られたところだが、19歳という若さで息子の「土御門天皇」(つちみかどてんのう)に天皇の座を譲り、和歌以外にも書画、管弦(琵琶など)、蹴鞠、水練(すいれん)、相撲、笠懸(かさがけ:弓矢の騎射)など諸芸を磨くことに力を注いだ。さらに武道にも秀で、自ら日本刀を打ったと伝えられるほど、歴代皇族の中でも異彩を放つ、天才肌の天皇である。
◇中でも、銘刀「菊御作」(きくごさく)は、後鳥羽上皇が残した最も偉大な文化遺産のひとつである。菊御作は数振現存しており、国宝・重要文化財に指定されている。
後鳥羽上皇がらみの雑文復刻の復刻です。
【復刻】
2022.01.12
今年の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」は、北条義時を主人公に平安時代末期の武士の台頭から、鎌倉幕府の樹立、貴族側の反撃承久の乱あたりまで描かれるものと思う。後半は後鳥羽上皇も目立つ役回りになると予想する。2年前の正月に掲載した雑文を再度アップ。
<追記>物語は承久の乱まで行かずに、もっと前の時点までで終わるのかもしれない。
【復刻】
2020年1月の記事を復刻
◇気まぐれ録画のテレビ番組を見た。面白かった。NHK[BSプレミアム] 1月4日(土) 午後7:00~午後9:00 新春英雄たちの選択スペシャル「百人一首」
◇お正月の風物詩、カルタでおなじみの「百人一首」(ここでは小倉百人一首を指す)。1人1首100人の和歌が納められている。平安時代を中心に7~13世紀のスター歌人が勢ぞろいした、いわば王朝ベストアルバムである。
<番組紹介は以下の通り>
■百人一首!名歌集はなぜ生まれたのか? 選者・藤原定家と後鳥羽上皇の愛憎渦巻くドラマ。選歌に秘められた謎。競技かるたの極意とは?百人一首を徹底解剖!
■百人一首は平安時代を中心に500年にわたる王朝の名歌を収めたベストアルバム。だが、この歌集、よく知られているようで実は謎が多い。名歌はどうやって生まれたのか?天皇から僧侶までの歌人は、なぜこの100人が選ばれた?番組は、選者・藤原定家と後鳥羽上皇の愛憎渦巻くドラマを軸に、百人一首誕生の秘密に迫っていく。クイーンとのかるた大会も開催。王朝の雅に浸りたい歴史ファン必見!百人一首を徹底解剖する特別企画
■百人一首は王朝絵巻、古代~中世550年の歌には時系列的に読み手に番号がつけられている。1番は天智天皇、17番在原業平、57番紫式部、86番西行、最後99番後鳥羽院、100番その息子の順徳院といった具合である。王朝時代のルーツから終焉までを網羅している。
■百人一首は藤原定家が選んだ秀歌撰である。定家は19歳から74歳まで自筆の日記を書いている。明月記である。それによってかなりの「人となり」がわかる。生まれは平安時代の末期、武士の台頭・源平の合戦の時期を生きている。まわりと相いれない定家の斬新な和歌にその才能を見抜いたのが18歳年下の後鳥羽上皇である。上皇は乱世により大きく人生を振り回された。わずか4歳で皇位についたが、安徳天皇とともに海中に沈んだ三種の神器の剣がない状態での即位であった。19歳で退位し上皇となってからは蹴鞠や歌舞音曲、刀剣制作などに打ち込んだ。そしてそれ以上にのめりこんだのが和歌であった。歌の力で失われつつある王朝の権威を取り戻そうとした。そのために必要だったのが時代の先を行く定家の斬新な和歌だった。2人の化学反応が王朝文化に革命を起こす。しかし時代の流れに巻き込まれ2人は仲たがいする。
<以下はいつもの私の雑文>
◇テレビ番組では途中に再現ドラマが入り、これが結構面白かった。膨らませて連続ドラマが作れそうだが、時代的に視聴率がとれないので大河ドラマにはならないでしょうね。
◇小倉百人一首は勅撰の和歌集ではないが、承久の乱を起こし、晩年は隠岐の島に流刑となった後鳥羽院が大きくかかわっていたというドラマの筋書きはうなづける。対立したとはいえ和歌の同好の士、後鳥羽院には心の底では最後には許しあっていたのでしないか。百人一種には「風」がうたわれた和歌が多いがそれは「隠岐の風」を意識していたのではないかという。先年亡くなった我が家のばあちゃんは、テレビで相撲をみていて隠岐の海がでてくると、しょっちゅう後鳥羽院の歌を声高に歌っていた。「われこそは新島守よ隠岐の海の 荒き波風心して吹け」。元気いっぱいの後鳥羽院は、さぞかし都に戻りたかったでしょうね。テレビの再現ドラマでは「隠岐の院」と呼んでいた。すんなり受け入れられた。
◇百人一種のカルタは最近はほとんどやってないが、一時は正月に集中的にやった。いつまでも頭に入らない歌があり、上の句を詠んで下の句がわかるのはせいぜい70%くらいだった。今はもうさらに忘れているものが多い。家族それぞれひいきの札がありそれだけは他人にとらせまいとがんばった。
◇歌の解釈はわからなくても耳から入って覚えたものは結構覚えているとも言える。英語も文法など後回しでいきなり会話・ヒアリングから入った方が身につくのには早道かも。
◇小学生の頃は坊主めくりをした。今時こんな遊びをする家庭はほんとに少ないのでしょうね。
◇宝塚歌劇団の生徒さんには百人一首からつけた名前が多かった。昔はほんとに百人一首カルタが広く親しまれていたと想像できる。
◇昔の和歌には「歌枕」が多く読み込まれている。仙台の近くでは、末の松山、沖の石、松島の雄島など。名取にお墓がある実方中将(藤原実方朝臣・51番)は「歌枕見てまいれ」と言われて陸奥の国に来た。百人一首にも親しみがわく題材がある。
◇小倉百人一首には数々の謎が隠されているといわれている。推理小説の題材にもなっている。選ばれた歌人は不幸な人生を歩んだ人が多いとかあまりに下手な歌が選ばれているとか。人気があって、広くみんなの目が行き届くといろいろ詮索することになるのだろう。
◇「親子して千と百とを詠みえらみ」こんな句があったと思う。おかげで、親の藤原俊成→千載和歌集、子供の藤原定家→百人一首と簡単に覚えられた。 → 【訂正】 御父子して千と百とをおんえらみ が正しいようだ
◇正月、肩の凝らない番組を楽しんだ。
1月1日(木) の日記 百人一首
12月31日(火) の日記 ウルトラクイズをまだやっていた
12月6日(金) の日記 復刻 昭和19年に起きた昭和東南海地震
11月22日(金)の日記 今日はいいフロの日
10月31日(木)の日記 AIによる自動音声
8月27日(火)の日記 再びユウガオの話 ラジオ深夜便から
12月31日(火) の日記 ウルトラクイズをまだやっていた
12月6日(金) の日記 復刻 昭和19年に起きた昭和東南海地震
11月22日(金)の日記 今日はいいフロの日
10月31日(木)の日記 AIによる自動音声
8月27日(火)の日記 再びユウガオの話 ラジオ深夜便から
Posted by OOAKAGERA at 22:12
│ざれごと たわごと