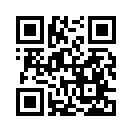2020年12月07日
12月7日(月)の日記 昭和東南海地震 復刻
1944年12月7日、太平洋戦争末期、東海地方で大きな地震が発生した。昭和東南海地震である。以下に記す。
亡きばあちゃんの昔の日記掘り起し 2020.04.18 転載および復刻
家の片づけで見つけた亡きばあちゃんの昔の日記発掘。本日は昭和19年12月7日編。
ばあの日記は、古い漢字・仮名づかいで私には読み取れないところも多々あり手強い。
その中で気になったのが昭和19年12月7日の東海地震(昭和東南海地震)に出くわした様子の記述。
<空から空襲、地上は地震と「袋のネズミ」>で死も覚悟した様子が読みとれた。この地震は多数の死者が出たとのことだが戦時中の情報統制がありほとんど報道されず今もあまり知られていないように思われる。もう少しこの地震の経験者の話を聞いてみたい気がしていたが先日テレビで取り上げていた。結構充実した内容で昭和東南海地震のことがよくわかった。
鳥見足止めで家にこもらざるを得ず、ためていたその録画をゆっくり見ながらメモをした。以下の通り。家で時間をもてあましている方、よかったら読んでください。
■■■■■
歴史秘話ヒストリア「隠された震災 昭和東南海地震」
地上NHK総合 2020/3/11(水)22:30-23:20(50分) 制作;大阪NHK
◇現代では巨大災害直後は被災地の情報はテレビや新聞、ネット等によって世界にすぐ伝えられる。
◇ところが今から80年ほど前、報道されなかった巨大災害があった。昭和東南海地震である。その被害報告が詳しく報道されなかった。それで「隠された震災」と言われている。
◇1941年12月8日/太平洋戦争開戦、1944年7月/サイパン島日本軍全滅、10月/レイテ島海戦日本軍大敗、12月7日/ 昭和東南海地震、1945年9月/日本降伏。太平洋戦争のさなか、戦局は悪化の一途をたどっていた時期にあたる。
◇しかも、この地震は、現在最も警戒されている「南海トラフ大地震」と同じものである。
【エピソード1】巨大地震はなぜ隠されたのか?
◇地震発生までの日本国内の動き
◇1年3ケ月前、それは始まっていた。鳥取大地震である。
◇鳥取市鹿野地区の水路に残された断層のズレ。1943年9月10日、M7.2鳥取地震発生。巨大直下型地震。震源に近い鳥取市街のほとんどの家屋はほぼ倒壊した、死者1088人、負傷者3千人以上。翌日からこの地震はさかんに報道された。そのことで全国から義援金が集まり、いち早い復旧が果たされた。この頃までは震災は隠されていなかった。
◇しかし兆候があった。1943年10月28日の貴族院予算委員会で鳥取地震の復興について質疑が行われていた。質問に立った貴族院議員大河内輝耕は直前に被災地を視察していた。質問にて、鳥取の被害状況について「今回の鳥取市における地震災害は非常に大きい、ただ幸いなことに火事が少なかった」と説明中、東条英機首相によって突然遮られた。「ご意見を賜るのは結構だが、政府としては、目下戦争中であり国内における災害を敵側としては誇大に取り扱っている、今の速記が直ちに外にでることのないように注意してもらいたい」と述べた。議員の発言を総理大臣がさまたげるのは議会の規定に違反する行為である。東条はなぜそのような行動をとったか・・・
◇日本がダメージを受けているということを知られることが敵に対しても日本国民に対してもよくない影響を与えるというふうに考えたのだろう(聖心女子大土田教授)。
◇国家が災害情報をコントロールする動き、それは研究機関にも及ぼうとしていた。
◇昭和東南海地震1年1ケ月前。日本の地震研究の中心、東京帝国大学地震研究所助教授だった萩原尊礼は、現地調査から帰って新聞に請われるままに鳥取地震の状況を書いた。ところがこれが新聞に載るとさっそく所長に呼ばれ「今後このようなことをしてはならない」とひどく叱られた。このことがあってからは所員の新聞雑誌への寄稿は所長があらかじめ検閲するということになってしまった。さらに、同時期、所員たちは陸軍所属という扱いに変えられた。そして地震観測の技術を応用しアメリカ軍が投下した機雷を探る、といった研究に従事した。
◇そうした中、せまりつつあった東南海地震、一人のベテラン研究者がその兆候に気づいた。それは、地震の神様と言われた元東京帝国大学教授今村明恒であった。今村は論文で「遠州東南地震塊の傾動に就いて」として衝撃的な事実を述べている。静岡県西部の海沿い(御前崎付近)で、
過去数十年で30-40cmに及ぶ地盤の沈下がみられる、というものであった。さらに、今村は、江戸時代にこの地域で起きた巨大地震(安政地震)の時にも同じ異変が起きたことも現地調査などからつきとめた。
◇のちに東南海地震と呼ばれる、遠州灘と駿河湾の地震に注目しないといけないと警告を発していた。地震災害を軽減するということに対して積極的に発言しているし、今から観測をして次の地震に備えようというメッセージであった。(関西大教授 林能成氏)
◇しかし、今村の論文は、国をあげて戦争を優先する中ほとんど注目されなかった。
◇地震発生13日前。1944(昭和19)年11月24日、東京への本格的な空襲が始まった。
◇当時、日本軍は南太平洋の島々で次々と敗北、そこにアメリカ軍が日本を爆撃するための基地を建設した。
◇昭和東南海地震は、苦境のさ中の日本に襲いかかろうとしていたのだ。
◇戦争への協力を求められた日本の地震研究者たち。その当時日本の地震研究は世界のトップレベルにあった。
◇測定データを検証し、東南海地震の兆候をつかんでいた地震学者の今村明恒は実はこの20年余り前の関東大震災(1923年)についても警告を発していた。
◇関東大震災をきっかけに設立されたのが東京帝国大学地震研究所である。地震の専門家はもちろん、建築・物理といった幅広い分野の人材を招き、地震の総合的研究がされていた。
◇また、現在の気象庁にあたる中央気象台は、地震計を110台を全国各地に設置した。世界にも例のない地震の一大観測網であった。
◇そうした地震研究にも戦争の影が・・・そこへ昭和東南海地震の発生。
【エピソード2】 その日すべては隠された
◇三重県紀北町に住んでいる山下正寿さん(82歳)は当時国民学校1年生(7歳)、1944年12月7日午後1時36分。立つことも出来ない激しい揺れ。震度6強、東南海地震の発生。ガタガタという揺れ、その日の恐怖が耳に焼き付いている。自宅から海岸まではわずか50m。あわてて家に逃げ帰った山下さんは、「津波」という大声でわけもわからず父に手を引かれて高台へ。そこで生まれて初めて津波で集落が押し流されてゆくのが見えた。その直後、湾内の海水が全部引いて海の底が見えた。
◇M7.9、8つの県で震度5以上。三重県では地震と津波で家屋の被災1万2000、死者およそ400人に及んだ。
◇昭和東南海地震発生と同時刻、愛知県庁の1室で会議が開かれようとしていた。出席者の中心は陸軍中将岡田資。日本の軍需産業の一大拠点であった東海地方の工場を指揮・監督する立場にあった。
◇激しい揺れが2分ほどでおさまると、会議席上に工場の被害状況の速報が入る。被害は多くの軍需工場に及んでいた。1年前に操業を開始したばかりの中島飛行機半田製作所は、多くの建物がつぶれ勤労動員の生徒など153人が犠牲になった。
◇岡田は地震発生から3日間かけて被害状況を調べた。軍需工場の全壊1731、半壊1281、津波による流失81棟。東海地方の軍需工場は壊滅的打撃を受けた。
◇昭和東南海地震2分後、震源からおよそ300kmの東京ではゆったりとした揺れがおよそ10分以上続いた。揺れが収まって、しばらくすると各新聞社に内務省からの連絡が入った。
「災害現場の写真を掲載してはならない。軍需工場や鉄道の被害など戦力低下の推測につながることがらを掲載してはならない」というものであった。
◇こうして国による昭和東南海地震の隠蔽が始まった。
◇昭和東南海地震翌日。(昭和19年12月8日)。報道を制限された新聞は翌日1面には軍服姿の昭和天皇の写真が掲載された。各紙いずれも同じ。地震の翌日は太平洋戦争開戦3年目の日、そのため各紙は戦意高揚の記事を全面に掲載。一方で地震に関する記事はわずかであった。被害の数には一切ふれていなかった。
◇東南海地震の地域は重要な軍需産業地であったので被害は一切外に出さない。当時の新聞記者の話を聞くと報道も自由にはできなかったとのことだ。(兵庫県立大 木村教授)
◇昭和東南海地震3日後。(12月10日) 夜。岡田中将に訪問客があった。中央気象台長藤原咲平、この時藤原が何を話したか…推測、「今後も大きな地震が発生することへの警戒が必要、当局者は十分注意すべきです」
◇大きな地震が起きた後、ひとまわり小さいような地震が起きて、直下地震なら被害が出ることがある。だからそれに備えよ」というメッセージ。(関西大 林教授)
◇しかし岡田は4日後、愛知県庁にて、工場などに動員されている若者に訓示。ねぎらいの後、今回の地震は、昨夜来訪された藤原博士の明言するところでは、遠州灘西方の海中に震源を有するものであって、「若干の被害があったのである。しかし、当地区内大多数の工場には生産に及ぼす影響もなく、被害皆無の工場も少なくないのである。自己の工場に被害を受けた人々に相当の衝撃を与えたらしいが、大局的にみればさしたることではない」。昭和東南海地震の被害について岡田は被害の全容、学者の警告を承知していたはずにもかかわらず「さしたることはない」と述べた。
◇日本にとって厳しい戦局を打開するには、1機でも多く、少しでも早く飛行機を作って前線に送り出すことだという風に彼は自分の任務を認識しており、飛行機の生産を最大限高めるためにはどうしたらよいか考えた時に、正確な情報を伏せたことによって人々が落ち込むこのを防ぐ、真実を隠すようなウソをついたり、あおるような演説をしているように見えたり、ということになる(聖心女子大土田教授)
◇このあと岡田は、速やかな工場再開のために突貫工事を命じる。被災地に配備された軍を動員、あらゆる人材、資材が軍需工事用に振り向けられた。
◇内務省通達による震災報道の制限、軍需産業復旧のための被害の黙殺、こういったことから昭和東南地震は隠された。
◇厳しい制限の中、事実を記録するため被災地を歩き回る人々がいた。地震研究者たちである。直後に作成されている3つの地震津波の報告書が残されている。①中央気象台、➁名古屋帝国大学名古屋地方気象台、③東京帝国大学地震研究所。地域ごとの倒壊家屋や犠牲者の数、津波到達時刻や高さ、被災者への聞き取りまで含む昭和東南海地震の詳細な記録である。
◇当時の地震学、地震関連の学問のレベルが非常に高かった。情報統制下でいろいろな制限があってもそんなに障害と思わないで非常に的確に調査されたのではないか。(名古屋大 武村客員教授)
◇調査を行った1人、東京帝国大学地震研究所の宮村摂三。大きな被害のあった工場などの地盤に注目、するとほぼ例外なく泥質沖積層と呼ばれるやわらかい地盤の埋め立て地に建てられていた。堅固な地盤上の建物の被害との差は歴然だった。宮村は埋め立て地に建つ軍需工場などについて提言している。「あたかも爆弾の落ちるところの決まっている爆撃のようで、そこへわざわざ重要施設を持っていくという愚はなんとしても避けなければならない」
◇しかし、こうした研究者たちの言葉を政府が顧みることはなかった。調査報告書はそのまま捨て置かれた。
◇昭和東南海地震6日後(12月13日)、被災した名古屋に追い打ちとなる災難が降りかかった。空襲である。それまで東京方面に多く飛来していたB29が、地震後の混乱をねらうがごとく現れた。爆撃目標は軍需工場だった。日本政府はやっきになって隠したが、アメリカはすでに地震を知っていた。「壊滅的な地震が日本の中部を襲った。震源は日本の東岸から100マイルの日本海溝の可能性がある。軍需産業は地震による津波で被害を受けた(ニューヨークタイムス1944.12.9)
◇地震の波は地球の中を伝わってしまう。あの頃は世界レベルの地震観測網があるのでどこで地震が起きたかがわかってしまうので、隠して隠せるものではなかった(関西大 林教授)
◇まったく無駄だった地震の隠蔽、その一方で政府が顧みなかった危機が迫っていた。
◇いにしえから日本は無数の地震に襲われてきた。現代のような防災対策等のなかった時代、それでも人々は出来る限りの策を講じた。それは地震の規模や得られた教訓を後世に伝えることである。
◇三重県鳥羽市の常福寺の石碑には、江戸時代の安政東海地震のことが記されている。波の高さ22m。
◇大阪市内には、安政南海地震での教えが「大地震両川口津浪記石碑」として残されている。「大地震があれば津波が起きる、津波は沖から来るばかりではない、水の勢いも高潮とは異なる、これらの内容を後世に伝えるため、文字に墨をいれるように」。地元の人たちは今も石碑に従い墨を入れ、教えを心にきざんでいる。
◇こうした自然災害伝承碑は、国土地理院の調査で全国に415基確認されている。ところが、昭和東南海地震のものは1基だけである。
◇大地震にもかかわらず戦時中ほとんど知られることのなかった震災、これで終わりではなかった。
【エピソード3】 その後悲劇は終わらない。
◇昭和東南海地震37日後、1945年1月、東南海地震の被災地は再び地震に見舞われた。昭和20年1月13日の、M6.8三河地震である。
◇被害はおよそ15km四方という狭いエリアに集中、しかしその猛威は東南海地震を上回った。愛知県東部を中心に工場や役場、学校などの大きな建物が屋根だけを残し、つぶれた姿があちこちでみられた。
◇愛知県蒲郡市、宗徳寺の境内に今も三河地震の痕跡がある。地震の時に西側の方が隆起して段差が生じた。三河地震は活断層が総延長28kmにわたって動いた直下型地震で、1月前の昭和東南海地震に誘発されて起きたと言われ、犠牲者は2306人に及んだ。
◇15年前、2つの地震について500人ほどに聞き取り調査を行った(兵庫県立大学 木村教授)>
◇すると体験者は初め思うように話せなかった。軍部からの情報統制の中で上の人から「外にもらしてはいけない」と言われていて心の中にしまい込んだまま戦後を迎え、一生懸命当時のことを思い出しながら話しているうちにどんどんと「あの時は大変だった」と話が拡がっていく、
そういった、他の地震とは違うかたちのインタビューであった。
◇証言からは、情報統制がもたらした弊害も浮かび上がった。例えばライフラインひとつにしても、家の再建ひとつにしても、何をどこで支援を受けなければならないか、そういった情報が全く入らない。外からも支援が来ず、自分たちもどうしていいのかわからない、そういう中で必死に対応されていた、
◇愛知県安城市城ケ入町。2つの大地震で壊滅的被害を受けた。聞き取り調査に答えた岩瀬繁松さん(92歳)。地震当時からここに住んでいる。東南海地震が起きた時17歳であった。立っていることが出来なくて、家が横揺れで今にも倒れそうになった。けれども75度くらい傾いてその状態で地震はとまった。ほんと怖かった。しかし母1人、子1人の岩瀬さんには家の修理は困難だった。行政からの援助は、1.5mくらいの柱の切れ端を「修理せよ」と言って支給されたがもちろんぜんぜん使い物にはならなかった。1月13日の大地震(三河地震)になった。避難の指示もなくただこわれた家にいた岩瀬さん母子に三河地震が襲い掛かる。岩瀬さんは地震の衝撃で家の外に投げ出され奇跡的に助かった。しかし母親は倒壊した家の下敷きとなって亡くなった。すでに父親も亡くしていた岩瀬さん、他に家族はなく1人になった。「おふくろさんは私を大事に育ててくれ、ようやく1人前になったところでこんなことになった。私は夜があけても涙は止まらなかった」。
◇さまざまな理由で東南海地震が隠蔽されなければ救われた命があったかもしれない。
◇余震についての注意とか早めの修理補修とか、危ない家には住まないようにするとか、避難所のようなものを整備するとか、今の災害対応ならしっかり出来るようなことが戦争という状況の中でできなかった。それが三河地震の死者を増やしてしまった原因の一つだと思う、それは非常に悔やまれるところである(兵庫県立大 木村教授)
◇47日後。三河地震の10日後も名古屋市で空襲があり127名が命を落とした。名古屋市の空襲の犠牲者はすでに1000名を超えていた。その翌日(1945.1.24)岡田資陸軍中将が訪れたところは、日本放送協会名古屋中央放送局であった。普段ニュースを放送する夜7時、岡田はマイクに向かった。まず戦局の厳しさを語った後続けた。「勝利を確信しつつ工夫創意を忘れず、どんなに厳しい条件でも戦争遂行にまい進するように」と国民に訴えた。さらに「今なお進学だの試験だのに頭を悩ませている者のがいるのはいかがなものか、立て青年よ」。
◇その時17歳の青年だった岩瀬さん、岡田のいた放送局から30kmほどのところで、前に進もうともがいていた。ひとり壊れた家のガレキを朝から晩まで片付けていた。「寒い時期で、こたつなどなく、外でたき火。あの時ほどつらかったことはなかった。三河地震の時のつらさみじめなことはその後の人生にもなかった」
◇玉音放送。昭和東南海地震から8ケ月後戦争は終わった。
◇それから日本は戦後の高度成長期に入る。それから40年、昭和東南海地震を上回る地震災害は起きなかった。歴史的にも珍しいこの平穏な時期に日本経済は大きく発展した。戦後日本の繁栄を大地が支えた。
◇しかし1995年1月17日、阪神淡路大震災、2011年3月11日東日本大震災、私たちは地震と向きあわざるを得ないという現実を突きつけられている。
◇そして現在最も懸念されている南海トラフ巨大地震。昭和東南海地震と震源域が重なる。
◇地震学者武村雅之さん(名古屋大学教授)。来るべき巨大地震にどうそなえたらよいか昭和東南海地震から見つけ出そうとしてきた。当時の震度分布や被害状況を分析、現在の状況と重ね合わせて対策につなげようとしている。
◇元となった情報は、厳しい制限のもとで研究者たちが残したものである。「今、来るべき南海トラフ地震のことがいろいろ言われているが、実証的にちゃんと近代的な地震学が残したものというものは、東海地方であると昭和東南海地震しかない。だからそれがあるとないでは非常に違う。それはものすごく説得力がある、将来に対するメッセージではないかと思う。
◇昭和東南海地震75年後。2019年12月7日(昨年)、三重県尾鷲市では昭和東南海地震の津波で亡くなった人の慰霊祭が行われた。かって震災があったこと、そのことを語り継いでゆく、それが未来の人々の命を守ることにつながるはずだ。
最後までお付き合いいただき感謝申し上げます
写真と本文は関係ありません

亡きばあちゃんの昔の日記掘り起し 2020.04.18 転載および復刻
家の片づけで見つけた亡きばあちゃんの昔の日記発掘。本日は昭和19年12月7日編。
ばあの日記は、古い漢字・仮名づかいで私には読み取れないところも多々あり手強い。
その中で気になったのが昭和19年12月7日の東海地震(昭和東南海地震)に出くわした様子の記述。
<空から空襲、地上は地震と「袋のネズミ」>で死も覚悟した様子が読みとれた。この地震は多数の死者が出たとのことだが戦時中の情報統制がありほとんど報道されず今もあまり知られていないように思われる。もう少しこの地震の経験者の話を聞いてみたい気がしていたが先日テレビで取り上げていた。結構充実した内容で昭和東南海地震のことがよくわかった。
鳥見足止めで家にこもらざるを得ず、ためていたその録画をゆっくり見ながらメモをした。以下の通り。家で時間をもてあましている方、よかったら読んでください。
■■■■■
歴史秘話ヒストリア「隠された震災 昭和東南海地震」
地上NHK総合 2020/3/11(水)22:30-23:20(50分) 制作;大阪NHK
◇現代では巨大災害直後は被災地の情報はテレビや新聞、ネット等によって世界にすぐ伝えられる。
◇ところが今から80年ほど前、報道されなかった巨大災害があった。昭和東南海地震である。その被害報告が詳しく報道されなかった。それで「隠された震災」と言われている。
◇1941年12月8日/太平洋戦争開戦、1944年7月/サイパン島日本軍全滅、10月/レイテ島海戦日本軍大敗、12月7日/ 昭和東南海地震、1945年9月/日本降伏。太平洋戦争のさなか、戦局は悪化の一途をたどっていた時期にあたる。
◇しかも、この地震は、現在最も警戒されている「南海トラフ大地震」と同じものである。
【エピソード1】巨大地震はなぜ隠されたのか?
◇地震発生までの日本国内の動き
◇1年3ケ月前、それは始まっていた。鳥取大地震である。
◇鳥取市鹿野地区の水路に残された断層のズレ。1943年9月10日、M7.2鳥取地震発生。巨大直下型地震。震源に近い鳥取市街のほとんどの家屋はほぼ倒壊した、死者1088人、負傷者3千人以上。翌日からこの地震はさかんに報道された。そのことで全国から義援金が集まり、いち早い復旧が果たされた。この頃までは震災は隠されていなかった。
◇しかし兆候があった。1943年10月28日の貴族院予算委員会で鳥取地震の復興について質疑が行われていた。質問に立った貴族院議員大河内輝耕は直前に被災地を視察していた。質問にて、鳥取の被害状況について「今回の鳥取市における地震災害は非常に大きい、ただ幸いなことに火事が少なかった」と説明中、東条英機首相によって突然遮られた。「ご意見を賜るのは結構だが、政府としては、目下戦争中であり国内における災害を敵側としては誇大に取り扱っている、今の速記が直ちに外にでることのないように注意してもらいたい」と述べた。議員の発言を総理大臣がさまたげるのは議会の規定に違反する行為である。東条はなぜそのような行動をとったか・・・
◇日本がダメージを受けているということを知られることが敵に対しても日本国民に対してもよくない影響を与えるというふうに考えたのだろう(聖心女子大土田教授)。
◇国家が災害情報をコントロールする動き、それは研究機関にも及ぼうとしていた。
◇昭和東南海地震1年1ケ月前。日本の地震研究の中心、東京帝国大学地震研究所助教授だった萩原尊礼は、現地調査から帰って新聞に請われるままに鳥取地震の状況を書いた。ところがこれが新聞に載るとさっそく所長に呼ばれ「今後このようなことをしてはならない」とひどく叱られた。このことがあってからは所員の新聞雑誌への寄稿は所長があらかじめ検閲するということになってしまった。さらに、同時期、所員たちは陸軍所属という扱いに変えられた。そして地震観測の技術を応用しアメリカ軍が投下した機雷を探る、といった研究に従事した。
◇そうした中、せまりつつあった東南海地震、一人のベテラン研究者がその兆候に気づいた。それは、地震の神様と言われた元東京帝国大学教授今村明恒であった。今村は論文で「遠州東南地震塊の傾動に就いて」として衝撃的な事実を述べている。静岡県西部の海沿い(御前崎付近)で、
過去数十年で30-40cmに及ぶ地盤の沈下がみられる、というものであった。さらに、今村は、江戸時代にこの地域で起きた巨大地震(安政地震)の時にも同じ異変が起きたことも現地調査などからつきとめた。
◇のちに東南海地震と呼ばれる、遠州灘と駿河湾の地震に注目しないといけないと警告を発していた。地震災害を軽減するということに対して積極的に発言しているし、今から観測をして次の地震に備えようというメッセージであった。(関西大教授 林能成氏)
◇しかし、今村の論文は、国をあげて戦争を優先する中ほとんど注目されなかった。
◇地震発生13日前。1944(昭和19)年11月24日、東京への本格的な空襲が始まった。
◇当時、日本軍は南太平洋の島々で次々と敗北、そこにアメリカ軍が日本を爆撃するための基地を建設した。
◇昭和東南海地震は、苦境のさ中の日本に襲いかかろうとしていたのだ。
◇戦争への協力を求められた日本の地震研究者たち。その当時日本の地震研究は世界のトップレベルにあった。
◇測定データを検証し、東南海地震の兆候をつかんでいた地震学者の今村明恒は実はこの20年余り前の関東大震災(1923年)についても警告を発していた。
◇関東大震災をきっかけに設立されたのが東京帝国大学地震研究所である。地震の専門家はもちろん、建築・物理といった幅広い分野の人材を招き、地震の総合的研究がされていた。
◇また、現在の気象庁にあたる中央気象台は、地震計を110台を全国各地に設置した。世界にも例のない地震の一大観測網であった。
◇そうした地震研究にも戦争の影が・・・そこへ昭和東南海地震の発生。
【エピソード2】 その日すべては隠された
◇三重県紀北町に住んでいる山下正寿さん(82歳)は当時国民学校1年生(7歳)、1944年12月7日午後1時36分。立つことも出来ない激しい揺れ。震度6強、東南海地震の発生。ガタガタという揺れ、その日の恐怖が耳に焼き付いている。自宅から海岸まではわずか50m。あわてて家に逃げ帰った山下さんは、「津波」という大声でわけもわからず父に手を引かれて高台へ。そこで生まれて初めて津波で集落が押し流されてゆくのが見えた。その直後、湾内の海水が全部引いて海の底が見えた。
◇M7.9、8つの県で震度5以上。三重県では地震と津波で家屋の被災1万2000、死者およそ400人に及んだ。
◇昭和東南海地震発生と同時刻、愛知県庁の1室で会議が開かれようとしていた。出席者の中心は陸軍中将岡田資。日本の軍需産業の一大拠点であった東海地方の工場を指揮・監督する立場にあった。
◇激しい揺れが2分ほどでおさまると、会議席上に工場の被害状況の速報が入る。被害は多くの軍需工場に及んでいた。1年前に操業を開始したばかりの中島飛行機半田製作所は、多くの建物がつぶれ勤労動員の生徒など153人が犠牲になった。
◇岡田は地震発生から3日間かけて被害状況を調べた。軍需工場の全壊1731、半壊1281、津波による流失81棟。東海地方の軍需工場は壊滅的打撃を受けた。
◇昭和東南海地震2分後、震源からおよそ300kmの東京ではゆったりとした揺れがおよそ10分以上続いた。揺れが収まって、しばらくすると各新聞社に内務省からの連絡が入った。
「災害現場の写真を掲載してはならない。軍需工場や鉄道の被害など戦力低下の推測につながることがらを掲載してはならない」というものであった。
◇こうして国による昭和東南海地震の隠蔽が始まった。
◇昭和東南海地震翌日。(昭和19年12月8日)。報道を制限された新聞は翌日1面には軍服姿の昭和天皇の写真が掲載された。各紙いずれも同じ。地震の翌日は太平洋戦争開戦3年目の日、そのため各紙は戦意高揚の記事を全面に掲載。一方で地震に関する記事はわずかであった。被害の数には一切ふれていなかった。
◇東南海地震の地域は重要な軍需産業地であったので被害は一切外に出さない。当時の新聞記者の話を聞くと報道も自由にはできなかったとのことだ。(兵庫県立大 木村教授)
◇昭和東南海地震3日後。(12月10日) 夜。岡田中将に訪問客があった。中央気象台長藤原咲平、この時藤原が何を話したか…推測、「今後も大きな地震が発生することへの警戒が必要、当局者は十分注意すべきです」
◇大きな地震が起きた後、ひとまわり小さいような地震が起きて、直下地震なら被害が出ることがある。だからそれに備えよ」というメッセージ。(関西大 林教授)
◇しかし岡田は4日後、愛知県庁にて、工場などに動員されている若者に訓示。ねぎらいの後、今回の地震は、昨夜来訪された藤原博士の明言するところでは、遠州灘西方の海中に震源を有するものであって、「若干の被害があったのである。しかし、当地区内大多数の工場には生産に及ぼす影響もなく、被害皆無の工場も少なくないのである。自己の工場に被害を受けた人々に相当の衝撃を与えたらしいが、大局的にみればさしたることではない」。昭和東南海地震の被害について岡田は被害の全容、学者の警告を承知していたはずにもかかわらず「さしたることはない」と述べた。
◇日本にとって厳しい戦局を打開するには、1機でも多く、少しでも早く飛行機を作って前線に送り出すことだという風に彼は自分の任務を認識しており、飛行機の生産を最大限高めるためにはどうしたらよいか考えた時に、正確な情報を伏せたことによって人々が落ち込むこのを防ぐ、真実を隠すようなウソをついたり、あおるような演説をしているように見えたり、ということになる(聖心女子大土田教授)
◇このあと岡田は、速やかな工場再開のために突貫工事を命じる。被災地に配備された軍を動員、あらゆる人材、資材が軍需工事用に振り向けられた。
◇内務省通達による震災報道の制限、軍需産業復旧のための被害の黙殺、こういったことから昭和東南地震は隠された。
◇厳しい制限の中、事実を記録するため被災地を歩き回る人々がいた。地震研究者たちである。直後に作成されている3つの地震津波の報告書が残されている。①中央気象台、➁名古屋帝国大学名古屋地方気象台、③東京帝国大学地震研究所。地域ごとの倒壊家屋や犠牲者の数、津波到達時刻や高さ、被災者への聞き取りまで含む昭和東南海地震の詳細な記録である。
◇当時の地震学、地震関連の学問のレベルが非常に高かった。情報統制下でいろいろな制限があってもそんなに障害と思わないで非常に的確に調査されたのではないか。(名古屋大 武村客員教授)
◇調査を行った1人、東京帝国大学地震研究所の宮村摂三。大きな被害のあった工場などの地盤に注目、するとほぼ例外なく泥質沖積層と呼ばれるやわらかい地盤の埋め立て地に建てられていた。堅固な地盤上の建物の被害との差は歴然だった。宮村は埋め立て地に建つ軍需工場などについて提言している。「あたかも爆弾の落ちるところの決まっている爆撃のようで、そこへわざわざ重要施設を持っていくという愚はなんとしても避けなければならない」
◇しかし、こうした研究者たちの言葉を政府が顧みることはなかった。調査報告書はそのまま捨て置かれた。
◇昭和東南海地震6日後(12月13日)、被災した名古屋に追い打ちとなる災難が降りかかった。空襲である。それまで東京方面に多く飛来していたB29が、地震後の混乱をねらうがごとく現れた。爆撃目標は軍需工場だった。日本政府はやっきになって隠したが、アメリカはすでに地震を知っていた。「壊滅的な地震が日本の中部を襲った。震源は日本の東岸から100マイルの日本海溝の可能性がある。軍需産業は地震による津波で被害を受けた(ニューヨークタイムス1944.12.9)
◇地震の波は地球の中を伝わってしまう。あの頃は世界レベルの地震観測網があるのでどこで地震が起きたかがわかってしまうので、隠して隠せるものではなかった(関西大 林教授)
◇まったく無駄だった地震の隠蔽、その一方で政府が顧みなかった危機が迫っていた。
◇いにしえから日本は無数の地震に襲われてきた。現代のような防災対策等のなかった時代、それでも人々は出来る限りの策を講じた。それは地震の規模や得られた教訓を後世に伝えることである。
◇三重県鳥羽市の常福寺の石碑には、江戸時代の安政東海地震のことが記されている。波の高さ22m。
◇大阪市内には、安政南海地震での教えが「大地震両川口津浪記石碑」として残されている。「大地震があれば津波が起きる、津波は沖から来るばかりではない、水の勢いも高潮とは異なる、これらの内容を後世に伝えるため、文字に墨をいれるように」。地元の人たちは今も石碑に従い墨を入れ、教えを心にきざんでいる。
◇こうした自然災害伝承碑は、国土地理院の調査で全国に415基確認されている。ところが、昭和東南海地震のものは1基だけである。
◇大地震にもかかわらず戦時中ほとんど知られることのなかった震災、これで終わりではなかった。
【エピソード3】 その後悲劇は終わらない。
◇昭和東南海地震37日後、1945年1月、東南海地震の被災地は再び地震に見舞われた。昭和20年1月13日の、M6.8三河地震である。
◇被害はおよそ15km四方という狭いエリアに集中、しかしその猛威は東南海地震を上回った。愛知県東部を中心に工場や役場、学校などの大きな建物が屋根だけを残し、つぶれた姿があちこちでみられた。
◇愛知県蒲郡市、宗徳寺の境内に今も三河地震の痕跡がある。地震の時に西側の方が隆起して段差が生じた。三河地震は活断層が総延長28kmにわたって動いた直下型地震で、1月前の昭和東南海地震に誘発されて起きたと言われ、犠牲者は2306人に及んだ。
◇15年前、2つの地震について500人ほどに聞き取り調査を行った(兵庫県立大学 木村教授)>
◇すると体験者は初め思うように話せなかった。軍部からの情報統制の中で上の人から「外にもらしてはいけない」と言われていて心の中にしまい込んだまま戦後を迎え、一生懸命当時のことを思い出しながら話しているうちにどんどんと「あの時は大変だった」と話が拡がっていく、
そういった、他の地震とは違うかたちのインタビューであった。
◇証言からは、情報統制がもたらした弊害も浮かび上がった。例えばライフラインひとつにしても、家の再建ひとつにしても、何をどこで支援を受けなければならないか、そういった情報が全く入らない。外からも支援が来ず、自分たちもどうしていいのかわからない、そういう中で必死に対応されていた、
◇愛知県安城市城ケ入町。2つの大地震で壊滅的被害を受けた。聞き取り調査に答えた岩瀬繁松さん(92歳)。地震当時からここに住んでいる。東南海地震が起きた時17歳であった。立っていることが出来なくて、家が横揺れで今にも倒れそうになった。けれども75度くらい傾いてその状態で地震はとまった。ほんと怖かった。しかし母1人、子1人の岩瀬さんには家の修理は困難だった。行政からの援助は、1.5mくらいの柱の切れ端を「修理せよ」と言って支給されたがもちろんぜんぜん使い物にはならなかった。1月13日の大地震(三河地震)になった。避難の指示もなくただこわれた家にいた岩瀬さん母子に三河地震が襲い掛かる。岩瀬さんは地震の衝撃で家の外に投げ出され奇跡的に助かった。しかし母親は倒壊した家の下敷きとなって亡くなった。すでに父親も亡くしていた岩瀬さん、他に家族はなく1人になった。「おふくろさんは私を大事に育ててくれ、ようやく1人前になったところでこんなことになった。私は夜があけても涙は止まらなかった」。
◇さまざまな理由で東南海地震が隠蔽されなければ救われた命があったかもしれない。
◇余震についての注意とか早めの修理補修とか、危ない家には住まないようにするとか、避難所のようなものを整備するとか、今の災害対応ならしっかり出来るようなことが戦争という状況の中でできなかった。それが三河地震の死者を増やしてしまった原因の一つだと思う、それは非常に悔やまれるところである(兵庫県立大 木村教授)
◇47日後。三河地震の10日後も名古屋市で空襲があり127名が命を落とした。名古屋市の空襲の犠牲者はすでに1000名を超えていた。その翌日(1945.1.24)岡田資陸軍中将が訪れたところは、日本放送協会名古屋中央放送局であった。普段ニュースを放送する夜7時、岡田はマイクに向かった。まず戦局の厳しさを語った後続けた。「勝利を確信しつつ工夫創意を忘れず、どんなに厳しい条件でも戦争遂行にまい進するように」と国民に訴えた。さらに「今なお進学だの試験だのに頭を悩ませている者のがいるのはいかがなものか、立て青年よ」。
◇その時17歳の青年だった岩瀬さん、岡田のいた放送局から30kmほどのところで、前に進もうともがいていた。ひとり壊れた家のガレキを朝から晩まで片付けていた。「寒い時期で、こたつなどなく、外でたき火。あの時ほどつらかったことはなかった。三河地震の時のつらさみじめなことはその後の人生にもなかった」
◇玉音放送。昭和東南海地震から8ケ月後戦争は終わった。
◇それから日本は戦後の高度成長期に入る。それから40年、昭和東南海地震を上回る地震災害は起きなかった。歴史的にも珍しいこの平穏な時期に日本経済は大きく発展した。戦後日本の繁栄を大地が支えた。
◇しかし1995年1月17日、阪神淡路大震災、2011年3月11日東日本大震災、私たちは地震と向きあわざるを得ないという現実を突きつけられている。
◇そして現在最も懸念されている南海トラフ巨大地震。昭和東南海地震と震源域が重なる。
◇地震学者武村雅之さん(名古屋大学教授)。来るべき巨大地震にどうそなえたらよいか昭和東南海地震から見つけ出そうとしてきた。当時の震度分布や被害状況を分析、現在の状況と重ね合わせて対策につなげようとしている。
◇元となった情報は、厳しい制限のもとで研究者たちが残したものである。「今、来るべき南海トラフ地震のことがいろいろ言われているが、実証的にちゃんと近代的な地震学が残したものというものは、東海地方であると昭和東南海地震しかない。だからそれがあるとないでは非常に違う。それはものすごく説得力がある、将来に対するメッセージではないかと思う。
◇昭和東南海地震75年後。2019年12月7日(昨年)、三重県尾鷲市では昭和東南海地震の津波で亡くなった人の慰霊祭が行われた。かって震災があったこと、そのことを語り継いでゆく、それが未来の人々の命を守ることにつながるはずだ。
最後までお付き合いいただき感謝申し上げます
写真と本文は関係ありません

4月15日(火)の日記 新寺通りと周辺のお花見今年の実績
4月4日(金)の日記 公園の桜を鑑賞
3月25日(火)の日記 NHKラジオ深夜便 「鳥の雑学ノート」終了、残念
3月23日(日)の日記 単管バリケード 通行止め<ウマ>
3月19日(水)の日記 女優のいしだあゆみさん亡くなる
3月10日(月)の日記 今日は何の日。1945年東京大空襲の日
4月4日(金)の日記 公園の桜を鑑賞
3月25日(火)の日記 NHKラジオ深夜便 「鳥の雑学ノート」終了、残念
3月23日(日)の日記 単管バリケード 通行止め<ウマ>
3月19日(水)の日記 女優のいしだあゆみさん亡くなる
3月10日(月)の日記 今日は何の日。1945年東京大空襲の日
Posted by OOAKAGERA at 20:50
│日常生活